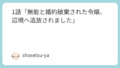制御室の障壁が復旧して数時間。
私は砦の簡素な個室に案内され、わずかな荷物を置いたところだった。
木製のベッドと机、そして窓のない石の壁。贅沢とは無縁の生活空間だけれど、不思議と心地よかった。
(静かで……無駄がない。こういう場所のほうが集中できるわ)
王都の宮廷では、シルクのドレスを着て笑顔を貼りつけ、何の意味もないお茶会に出ていた。
今の方が、よほど“自分らしい”。
翌朝、私は食堂で不思議な空気に包まれた。
――視線。
兵士たちが、遠巻きにこちらを見てひそひそ話している。
「昨日の障壁、あの子が直したって……」「でも王都で“無能”だったらしいぞ?」
「いや、あの術式……普通の魔導士じゃ理解すら無理だ。俺、あのタイプ見たことない」
昨日の出来事が、すでに砦中に広まっていたようだった。
無理もない。制御装置の再起動に使った術式は、千年前の古代魔術の一種だ。
今の魔導士教育では、まず教わらない。
私はパンをかじりながら、ちらりと隣の席を見る。
――カイラス司令官が座っていた。
……この人、本当に砦の司令官?
軍服姿のままパンを片手に読み物をしているその姿は、完全に「寝起きのお兄さん」だった。
とはいえ、昨夜の彼の言葉は忘れていない。
『……やるじゃないか、“無能”令嬢』
あれは――ほんの少しだけ、敬意が混じっていた。
「お前、今日から第二魔道障壁の維持班に入れ。お前がいれば多少マシになる」
カイラスはパンを食べながら、私にそう言った。
「承知しました。ですが……“多少”ではなく、“完全”に安定させてみせます」
「……ほう?」
彼の目が一瞬だけこちらを見た。口元が、ほんの少しだけ緩んでいた……気がする。
「言ったな。なら期待しておこう、“最弱”令嬢殿」
「そろそろ、その呼び方は似合わないと思うんですけど?」
「結果を出せば、考えてやる」
……意外と、こういうやり取りも悪くないかもしれない。
だがその午後、私は再び異常な魔力の気配を感じることになる。
(……これは、何?)
砦の北方から、得体の知れない魔力の波が押し寄せてきた。
しかも、通常の魔獣とはまるで異なる“構造”をしている。
(これは……魔導生物……? まさか、こんな辺境に)
そして私はまだ知らなかった。
その魔物こそが――王都の“誰か”が、私を試すために差し向けたモノであることを。
午後三時過ぎ、砦の北方監視塔から緊急の警報が鳴り響いた。
「警戒区域に未知の魔獣接近! 形状不明、複数反応あり!」
作戦室に兵士たちの声が飛び交い、現場は一気に緊張に包まれた。
私はすぐに制御室から飛び出し、展望塔の最上部へ向かう。
見下ろす先、灰色の荒野に奇妙な“影”が見えた。
――人型。だが、皮膚も肉もなく、全身が黒い魔素で構成されている。
(……あれは、魔導生物……!)
通常の魔獣とは違う。それは、古代魔術によって人工的に生み出された“生きた呪い”だった。
「距離、残り二百! 障壁が……また不安定に!」
第二魔道障壁の術式が揺らぎ、魔力の波がざわついた。
(間に合わない。あの障壁じゃ、侵入を防げない……)
私は判断した。――外に出るしかない。
「どこへ行く!」
背後から、鋭い声が飛んだ。振り返ると、カイラス司令官が睨みつけていた。
「障壁の修復に向かいます。外部から直接、核へ魔力を注ぎます」
「それは自殺行為だ」
「でも、誰かがやらなければ、砦は突破されます」
一瞬の沈黙。そしてカイラスは短く吐き捨てた。
「……死ぬな」
「ええ。死にません。――私は“無能”じゃないので」
魔導障壁の外は、魔素が濃く、空気そのものが重たい。
私は指先で魔法陣を描き、中心に古代語を紡ぐ。
「《制律開放――古式魔術、第六封、律動変換》」
瞬間、地面から金の光が奔り、空間を走る魔力の構成が変化する。
――重力、空間、速度。すべてが私の“言葉”によって律せられた。
「接触確認! 敵、突入態勢に入ります!」
魔導生物がこちらへ跳躍した。
「《結界展開・式ノ三:封呪陣》!」
私の足元から展開された結界が、魔物の身体を縛り上げる。
黒い魔素が火花を散らし、断末魔のような叫びを上げて崩れ落ちた。
――一撃。
「な……何だ、今の魔法……?」
遠巻きに見ていた兵士たちが唖然とする。
「砦の術士じゃ、あんな制御……絶対できないぞ……」
「彼女、本当に王都じゃ“無能”だったのか……?」
私は息を整えながら、背後を振り返った。
砦の壁の上、カイラスがじっとこちらを見ていた。
その視線に、初めて「恐れ」と「敬意」が混じっているのを、私は感じた。