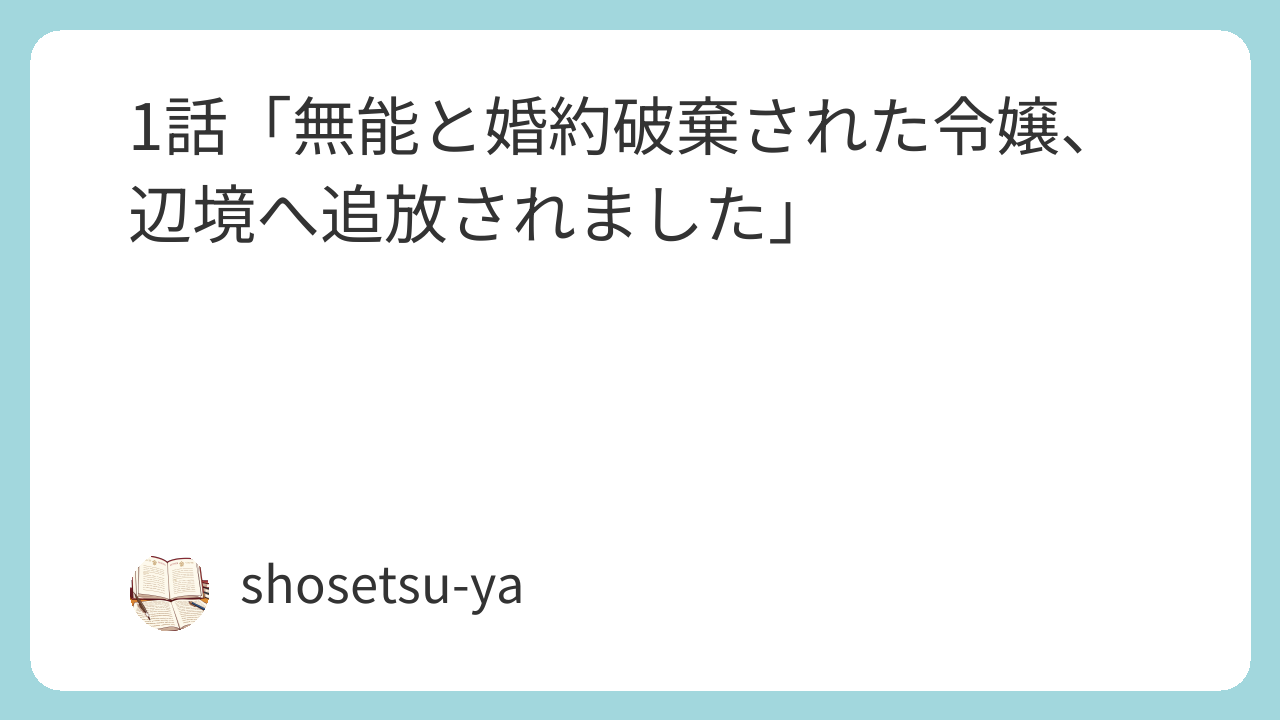「貴様との婚約は、今日限りで破棄する!」
その言葉が、私――ノクティア・エルヴァーンの人生を一変させた。
王国第二王子にして、王都一のエリート魔術士・リュゼル殿下は、貴族たちの前でそう宣言した。
「ノクティアには魔力がない。魔導士としての資質も皆無。これ以上、王家の名を汚すわけにはいかぬ!」
その場にいた者たちは一斉に私を笑った。
「お飾りのお嬢様だったのね」「可哀想に。まあ、自業自得よね」
ささやかれる声が、痛いほど耳に刺さる。
私はただ、静かに礼をして、その場を去った。
泣く? わけないじゃない。
――だって、本当の私は“無能”なんかじゃないのだから。
数日後、私は辺境への「左遷辞令」を言い渡された。
行き先は〈グランツ砦〉――魔物の被害が絶えない、危険地帯。
王都の人々は私が「幽閉される」とでも思っているのだろう。
けれど、私はむしろ笑いをこらえていた。
(辺境――いいじゃない。魔道の実験場にはぴったりだわ)
私は誰にも言っていない。けれど、本当の私は……
“魔力計では測れない、古代魔術の使い手”。
王都では「規格外」として無視されたけれど、力はずっと、私の中で眠っていた。
そして今、私はグランツ砦の前に立っている。
門が開き、現れたのは冷たい目をした軍服の男。長身で無駄のない動き。眼光鋭く、威圧感がある。
「お前が……ノクティア・エルヴァーンか」
「ええ。今日から魔道補佐として配属されます。よろしくお願いいたします」
男はしばらく私を見つめたのち、こう言った。
「俺はこの砦の司令官、カイラス・ヴァルドレン。ここでは無能は死ぬ。覚えておけ」
……ええ、重々承知よ。
むしろ、試してくれるならありがたい。
だって、私はもう――“ただの令嬢”じゃないのだから。
グランツ砦は、噂通りの場所だった。
無骨な石造りの外壁。常に鳴り響く警鐘の音。兵士たちの鋭い視線。
王都の華やかな宮廷とは正反対の、実戦の地。
私は司令官カイラスに案内され、中央棟の作戦室へと通された。
「ここが砦の中枢だ。魔道障壁の制御装置も隣室にある。今日からお前の担当だ」
「了解しました」
私の返事に、カイラスは一瞥をくれるだけ。歓迎の言葉など、ひと言もない。
――けれど、それでいい。むしろ落ち着く。
王都のような、笑顔の裏でナイフを突き立てられるような環境より、
目の前のこの冷たい空気の方が、よほど信頼できる。
配属初日から、いきなりトラブルが起きた。
「第二障壁が不安定です! 魔力供給が乱れています!」
兵士が血相を変えて飛び込んできた。
魔道障壁――それは砦を取り囲む魔法の防御網。これが崩れれば、魔獣の侵入を許す。
「修理班は?」「対応中ですが……中枢魔核が反応しません!」
作戦室がざわつく中、私は静かに手を挙げた。
「私が見に行きます」
「新入りがしゃしゃるな!」と誰かが舌打ちする。だが、カイラスが言った。
「……やらせてみろ。責任は俺が取る」
制御室には、古びた魔導機が並んでいた。王都では見たこともない構造。けれど、私にはわかる。
(これは古代王朝期の“双輪式魔核構造”。普通の術士じゃ起動すらできないわ)
私はそっと魔核に触れ、深く呼吸を整えた。
「《導きの理式、第七序列・再構成》」
誰にも聞こえないほど小さな声で、私は古代語を紡ぐ。
魔核が青白く光り、静かに回転を始めた。
「な……直った……?」
「え? 誰か触ったのか?」
「いや、彼女しかいなかったはず……」
部屋がどよめく中、私はただ、静かに微笑んだ。
「障壁、再稼働完了。魔力の流れも安定しています」
カイラスがこちらを見る。少しだけ、目が細められていた。
「……やるじゃないか、“無能”令嬢」
私は言葉を返さなかった。ただ、その呼び名がもう似合わないことを、
彼自身がいずれ気づくだろうと確信していた。